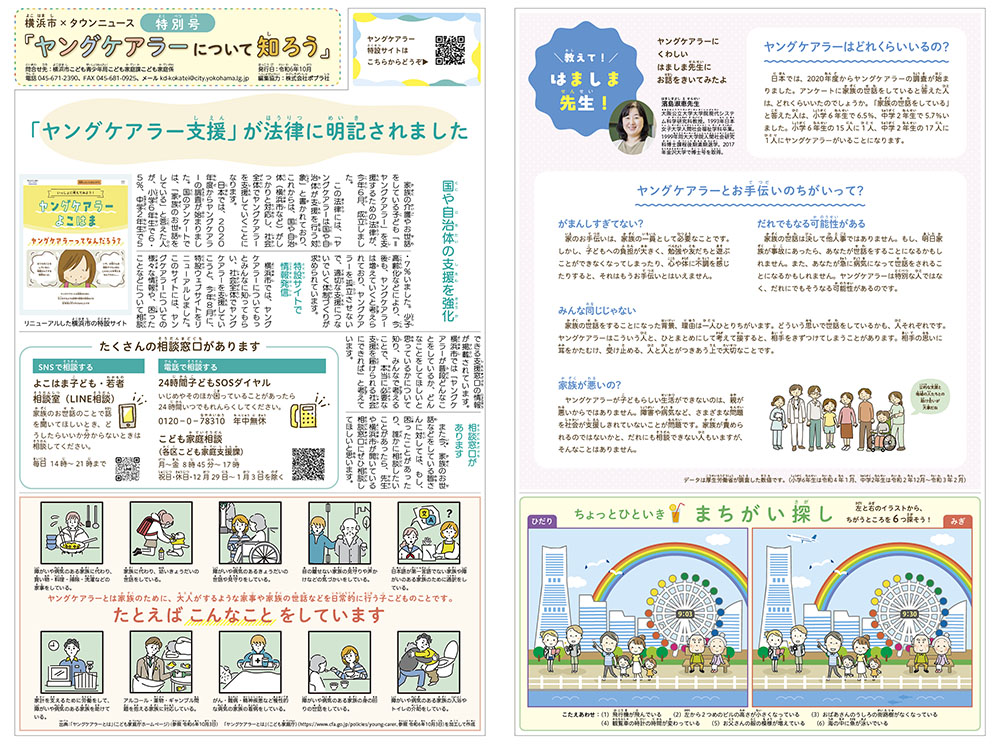祖父のケアから見えたもの

大学在学中に祖父が認知症を発症し、学業と並行して約3年間の介護を担った氏原拳汰さんは、現在ケアラー支援の分野で活動しています。祖父のケアをしながらの学生生活や、現在の道へ進むまでのこと、これから人生設計を考える若者へ伝えたいことをお話しいただきました。
元気だった祖父の異変に気づいた大学1年の冬
幼稚園の頃から両親と父方の祖父との4人暮らしだった氏原さん。祖父に異変が現れ日常が変化していったのは、大学1年生のときでした。
――おじいさまのケアが始まった経緯を教えてください。
「祖父はもともと、風邪も引かないくらいすごく元気な人でした。ずっと健康に過ごしていたんですけど、僕が大学1年の冬くらいから、物忘れが増えてきたんです。身体的にも衰えてきて、見守りが必要になってきたのがケアの初期。その後2年生になったときには自分でトイレができなくなり、病院で認知症と診断され、介護が必要な状況になりました」
――それまでお元気だったおじいさまが突然そのような状態になり、ショックも大きかったのでは?
「僕もそうでしたが、両親も含め、家族全員が祖父の変化に大きな戸惑いを感じていたことを覚えています。みんなが不安な気持ちな中で、精一杯なんとかやろうと家族全体で協力して祖父のケアと向き合っていました」
大学の授業を受けながら介護もこなしたコロナ禍
介護が本格的に始まったのは、ちょうどコロナ禍と重なった2020年。大学もオンライン授業になり、自宅にいる時間が増えた氏原さんが、共働きの両親が家を不在にしている時間を中心に祖父のケアを担いはじめることになりました。
――初めての介護。当時はどう感じていましたか?
「それまで介護というものを経験したことがなかったので、戸惑いがすごく大きかったです。でも、両親とも働いており仕事で忙しかったので、自然と僕も介護を担う流れになりました」
――介護の仕方はどのように学んだのですか?
「おむつの替え方とか、食事介助の方法とか、どういうふうに祖父と接すればいいのかみたいなのは、親が介護を行っている様子などを見て何となく学んでいたかと思います。ただ実際は、それだけでは対応できないようなこともたくさんあったので、我流の方法でやらざるを得ず、しばしば祖父に怖い思いをさせてしまったこともありました。あのときに誰かが、正しい介護のやり方について少しでも情報を伝えようとしてくれていれば、介護の質は大きく違っていたかもしれません。特に薬を飲んでもらうのが大変でした。ごはんを食べさせるのも一苦労でしたが、なんとか食べたと思っていざ薬を飲ませようとすると、『薬は嫌だ』って言い始めたり。祖父は徐々に感情の起伏が激しくなり、意思の疎通が難しくなることもありました」
――在宅しているとはいえ、授業との両立は大変だったのでは?
「オンライン授業を受けているときに、隣の部屋にいる祖父がベッドから落ちたり、トイレに行きたくなったりして『拳汰~!』って呼んでくるんですよね。それに対応しないといけないけど、でも授業も聞かなきゃいけないし…という状況で、もう、イヤホンを耳にしたまま祖父の部屋に慌てて駆け込み、授業中にも介護をせざるを得ないような毎日でした」
不安の中で芽生えた使命感、そして焦り…
介護生活がコロナ禍と重なったことで、日々の大学の授業と祖父の介護との両立を余儀なくされたという氏原さん。一方で、友人と遊んだりする自分の自由な時間はすっかり減ってしまったそう。
――介護をしながらの大学生活に、悩みやつらさはありましたか?
「いろいろありましたが、やっぱり一番は授業のことですね。コロナ禍の初期の頃はみんな結構楽観的で、“ひと月くらいで対面授業に戻れるんじゃないか”みたいな雰囲気があったのですが、僕は“対面に戻っちゃったら単位が取れずに卒業できなくなるのでは…”と不安になりました。結局オンライン授業の期間は1年半くらい続いたので、上限いっぱいまで単位を取って、なんとか介護と両立していました」
――生活の変化をどう受け止めていましたか?
「気づかないうちに、“介護は自分の役割なんだ”という思いが芽生えていた部分があったかもしれません。もちろん、“僕がやるべきなのかな…”と思うこともあったんですけど、でももう、そんなことも言っていられない状況でした」
――友だちと遊ぶ機会も減ってしまったのでは?
「激減しましたね。みんな大学生だったので、コロナ禍という状況であってもなんとか外に遊びに行ったりして、青春やモラトリアムを謳歌するみたいな。あとは就職活動を始めたり、いわゆる“ガクチカ(=学生時代に力を入れたこと)”のためにボランティアに参加して、その様子をSNSにアップしたりしていたんです。それを見たときには、なかなか外出ができない自分との差に焦りも感じました」
――ご自身はどのように息抜きをしていましたか?
「当時、サークル活動や友人関係にはどうしても制限がありましたが、オンラインで活動できる新聞のサークルには唯一入っていたんです。モヤモヤしたことがあったときには、そこで自分のケア経験をダーッと書き出して気持ちを整理したりしていました。そういう時間を持てていたのはよかったですね」
介護生活から導き出された道へ
これからの人生を決めていくはずの時期に祖父のケア中心の生活をしていた氏原さんは、将来に悩みを抱く一方で、ある気づきを得たといいます。
――そのような焦りの中、氏原さんは就活や進路についてどのように考えていましたか?
「当時は漠然と、祖父のケアを自分が担っている状況での就活は無理じゃないかなと悩んでいました。それに加えて、ケアのこととは関係なく、自分のやりたいことがそこまで定まっていなかったんです。でも、介護をしばらく続けたタイミングで、“これだけしんどいことをやってるのに、心理的なサポートを直接受けられたことがないな”と気づいたことをきっかけに、大学で心理学の授業を取り始めました。そこから、“心理職を目指してみてもいいのかな”と、大学院進学の方向に舵を切りました」
――ご自身の置かれた状況から、歩む道を見つけられたんですね。
「本当にたまたまですけどね。でも、いざ進学を目指して勉強しようとしても、当時は祖父が要介護5(要介護認定で最も重い段階)の寝たきり状態になっていて、つきっきりの介護でなかなか勉強の時間が取れませんでした」
困難に直面していたところ、大学4年の5月頃に状況が変わり、祖父が特別養護老人ホームに入ることに。
「もともと親は施設に入れることに抵抗があったんですけど、当時の担当ケアマネージャーさんが『氏原さんすごくがんばってるから、もう大丈夫だよ』って言ってくれたんです。それで家族全員が納得して施設に入ったんですが、施設入所後すぐに、亡くなってしまいました。祖父にとっては家が心地よかったんだろうなと思います」
――突然のお別れに、悔いはありませんでしたか?
「まさかそんなに早いとは思いませんでしたが、施設に入れる段階で覚悟をしていたことだったので。悲しさもありましたが、僕も両親も“やりきって送れた”という思いはあったので、そこにだいぶ救われましたね」
ケアラーから、ケアラー支援者に
氏原さんは現在、一般社団法人ヤングケアラー協会に運営メンバーとして関わっており、ヤングケアラー支援の専門職にも就いています。
――この道に進むことはどのように決断しましたか?
「自分の経験を出発点にして、そこからは自然な流れの中で決めていった形でした。それこそ自分が介護をしていたときに、実態としては僕も主介護者と同じくらいのケア負担を担っていたにもかかわらず、同居する孫(子ども)の存在に中々注目してもらえないな…と感じ、そこに対する支援が必要だと強く思ったんです」
自分の気持ちを大切にしてほしい
自身が介護を担っていたころは、支援サービスを活用することにハードルを感じ、自分が悩んでることや辛いことを吐き出すことにも抵抗があったという氏原さん。しかし、ケアが終わり、支援の活動において様々な人々と関わっていく中で、こう感じるようになったといいます。
「まずは、自分の気持ちをしっかり確かめて、受け止めることを大切にしてほしいです。周りに話したいときは話してもいいし、ひとりになりたいときはなってもいい。なんでもいいんです。無理はせず、少しでも自分が安心できる時間を作ってもらえたらいいなと思っています。その上で、もしよかったら選択肢のひとつとして、自治体の福祉的な支援を活用したり、ピアサポート活動に参加してみたりすることも、視野に入れてみてくれたら嬉しいです。気持ちを吐き出せる場があれば、それだけでも楽になれる部分はあると思います」
そして氏原さんは、こんな願いも抱きながら日々奮闘しています。
「今の社会では、介護を担うことで進学や就職などの選択肢が制限されてしまうことが少なくありません。介護が終わった後でしか、自分の人生を再スタートできないような仕組みは、見直す必要があると感じています。要介護者と一緒に過ごす時間の中でも、自分の将来を自由に考え、選択できる社会であってほしいと願っています」